いも判子を作ってみよう!
いも判子は名前の通り、いもで作る判子のことです。名前は聞いたことがあるけれど、実際に作ったことはないという方も多いかもしれません。今回はそんないも判子に挑戦してみます。
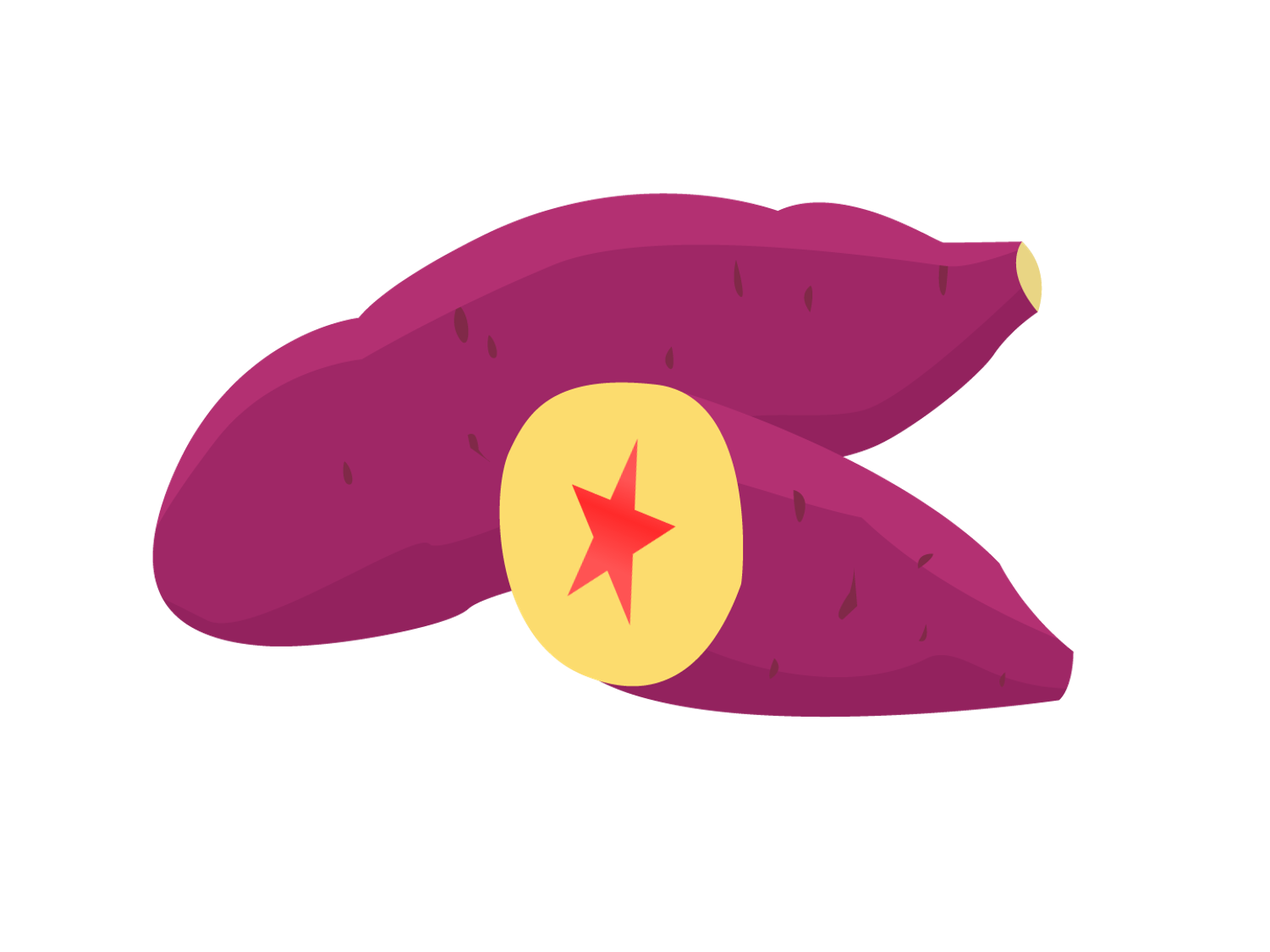
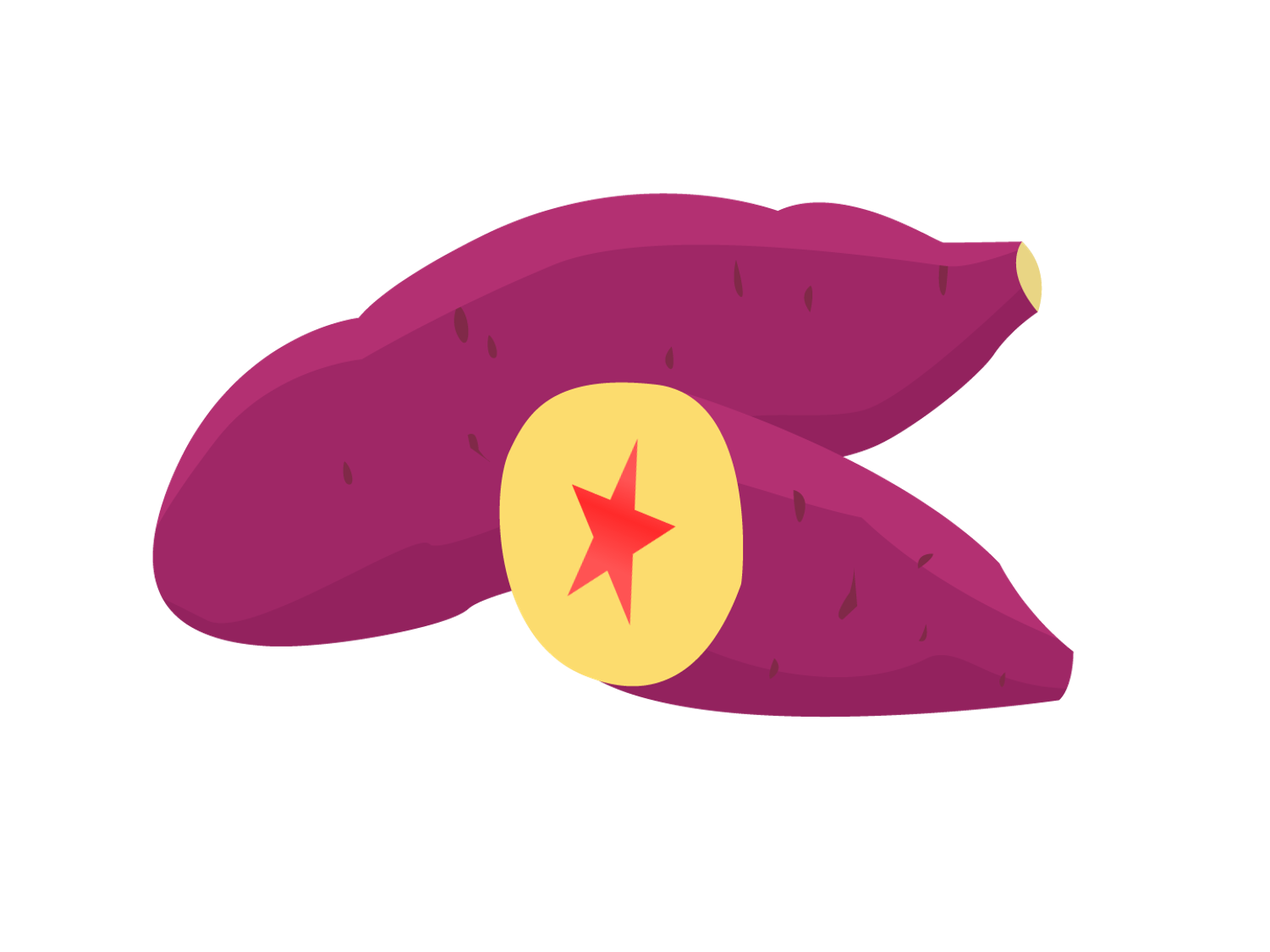
準備するもの
・さつまいも
・包丁
・まな板
・彫刻刀
・スタンプ台など色をつけるもの
・新聞紙(汚れが気になる場合)


方法
① さつまいもを包丁で半分に切る。
※端の部分を少し多めに切り落として使うようにしても大丈夫です

②彫刻刀などで好みの形にさつまいもの断面を削る。
※刃物を使うため、大人と一緒に行うようにしましょう。
③表面に色をつけて紙に押す。

今回の結果
いもを半分に切ってみると、断面の外側に白い液が見えます。これは「ヤラピン」と呼ばれる樹脂成分です。整腸作用があると言われています。こういう断面の観察をするのも面白いですよね。

ヤラピン含め余分な水分をふき取り、早速形を彫ってみます。
最初は簡単な形をと思い、ハート型に彫ることにしました。
下書きはせず、だいたいで彫っていき、赤のスタンプ台で色をつけて紙に押した様子がこちら。

少し表面がでこぼこしており、色のつきが良いところと悪いところがあります。綺麗な判子にするのって難しいのですね。最初に包丁で切るところから気を遣うべきだったかもしれません。
次はせっかくなので彫る形の難易度を上げてみます。OATアグリオの公式キャラクターであるアグリスくんを判子にしてみたく、挑戦してみました。
LINEスタンプの画像を参考に、下書きをしてから削っていきました。

緑色や黄色のスタンプ台が家になく、絵の具をつけて紙に押してみました。

色のつきは微妙なところですが、形は分かる仕上がりとなりました。やはりスタンプ台の方が色のつきは良さそうです。
表面のでこぼこ具合をどう整えるか、色をきれいにつけるためにはどうしたらよいかなど改良の余地がたくさんありますが、突き詰めるとキリが無さそうでしたので、今回の挑戦はここまでとします。
最後に
実際にいも判子を作ってみると、意外と難しいことが分かりました。昔の人がさつまいもを判子にしたのにはどのような背景があったのでしょうか。気になりますね。
さつまいも以外でも判子を作ってみると、素材による彫りやすさの違いなど色々比較できそうです。断面の観察をするのも面白いかもですね。野菜の切れ端でも楽しめますよ。
おまけ
いも判子は日持ちしませんので、判子部分を削り、残った部位を使ってドーナツを作りました。美味しかったです。


